フランスのSEEGガイドラインを見つけました.
Comprehensive review: French guidelines on stereoelectroencephalography (SEEG)
SEEGは50年以上前にフランスで発明
埋め込みに先立って明確な仮説が必要である
SEEGの適応と限界
epileptic zoneの仮説を確認し, 代替仮説を排除するために行う
最も適しているのは,
(1) FCDを含む皮質溝領域
(2) 深部皮質構造 (島弁蓋部, 大脳辺縁系など)
(3) 深部病変, 脳室周囲病変 (脳室周囲異所性灰白質, 視床下部過誤腫など)
SEEGは合併症発生率が低く, ほとんどの場合は硬膜下電極よりも好まれる.
両側探査は, 硬膜下電極よりもSEEGを優先する.
開頭手術を受けたことがある場合, 硬膜下電極よりもSEEGの方が好まれる.
MRI陰性の場合, 硬膜下電極よりもSEEGを優先する.
SEEGの限界は, サンプリングバイアスである
機能領域, 特に言語領域を正確に特定することは難しい.
病変がある側頭葉てんかん, 内側側頭葉てんかんにおいては, 大脳辺縁系外, 側頭葉外皮質, 対側側頭葉が関与している場合に適応.
また, てんかん原性ネットワークの境界と, 機能領域を探査するために適応となる場合がある
側頭葉てんかんでは, 海馬硬化症がないことがSEEGを実施する根拠となる
ウェルニッケ野の関与を疑う場合, 侵襲的探査が必須である
病変のある側頭葉外てんかんでは, 病変と矛盾がある場合に適応となることがある
また, 適応は病変の性質によって異なる.
視床下部過誤腫関連てんかんでは, 過誤腫とは無関係のepileptic zoneが疑われる場合にのみ適応
多発病変 (結節性硬化症, FCD, 結節性脳室周囲異所性, 海綿状血管腫) を伴うてんかんでは, epileptic zoneが限局しているという証拠がある場合に適応
片側性多小脳回では, 多小脳回の関与を判断するには最適である
両側性多小脳回では, 片側にepileptic zoneが示唆される場合に提案できる
小児てんかんでは, epileptic zoneの局在に仮説がある場合に提案することができる
乳児けいれんや睡眠中の電気的てんかん重積は, 局所的起源が示唆される場合に適応となることがある.
SEEGの計画
(1)epileptic zoneを定義する
(2)機能領域との関係を調べる
(3)外科的切除の可能性を評価する
を満たす必要がある
電極が6個未満の場合は, SEEGの妥当性に疑問を抱く必要がある
電極が15個を超える場合は, 計画された電極の数を減らすことを検討する必要がある
反対側に電極が必要な場合は, 可能であれば対称に配置する必要がある
両半球に同じ数の電極を配置する, 両側対称の検査は推奨されない.
特別な理由がない限り, 言語領域への電極の配置は避ける
側頭葉てんかんでは, 内側側頭構造 (海馬と扁桃体), 嗅内皮質, 中側頭回, 基底皮質, 上側頭回, 側頭極, 島皮質をサンプリングする
側頭葉外, 対側構造が関与する側頭葉てんかんでは, 他領域 (眼窩前頭皮質, シルビウス周囲領域, 側頭頭頂接合部, 対側内側側頭構造) をサンプリングすることができる
前頭葉てんかんでは, 側方化と局在化 (前方か後方か内側か背外側か) に関する予備仮説が必須
前頭葉てんかんでは, 解剖学的機能ネットワークに関与する構造を調査する必要がある
例えば, 前部前頭葉てんかんの場合は, 眼窩皮質, 前部帯状回, 島皮質
後部前頭葉てんかんの場合は, 補足運動野, 帯状回, 運動皮質
皮質の凸状性をサンプリングするには, 斜めの軌道を選択することが役立つ場合がある
中心領域のサンプリングでは, 出血性合併症のリスクを考慮
後方のてんかんでは, 伝播経路と機能的構造の関与を考慮しながら, 片側または両側の多葉サンプリングが必要になる
シルビウス裂周囲のてんかんでは, 島皮質と弁蓋部を調べる必要がある
島の探査は, 斜めまたは直交方向に実行できることがある.
病変性てんかんの場合, サンプリングは原因病変の種類によって異なる.
1つまたは複数の病変内に電極配置 (血管奇形または嚢胞性病変の場合を除く) と, 病変周囲に電極配置が必要
少なくとも1つの既知発作を記録することを推奨
複数の発作がある場合, 複数の発作を記録することは, それらの均一性を確認することに役立つ
FCD, 海馬構造において, 低頻度刺激で再現される発作は, 自発的な発作と同じ価値を持つ
SEEG中に, 持続する低速波が出現したり, 背景活動が悪化する場合は血腫を疑う
外科手術
患者の髪を切る必要はない.
術中出血リスクを最小限に抑えるために, 血管画像検査を行う
電極貫通部位は気洞に入る危険があってはならない.
合併症がない場合, 術後の集中治療室への入室は必須ではない
術後早期 (24 時間以内) に画像検査を推奨
電極の除去は, ベッドサイドまたは手術室で行うことができる
小児患者の場合, 局所麻酔または短時間の全身麻酔下で電極を除去し, 縫合を行うことを推奨
SEEGを実行するために許容される最小の頭蓋骨の厚さは2 mm
電気生理学的技術
CT, MRIは電極を装着した状態で実施
取得システムには少なくとも128 チャネル, 理想的には256チャネルが必要
50Hzフィルターを使用して記録しないように注意
ground contactsとreference contactsが異なる場合,
referenceは, 骨, 白質, 頭皮上のアクセス可能な場所 (CzとFzの間) にある記録接点から選択
groundは, 骨, 白質またはアクセス可能な皮膚部位(耳たぶまたは頭蓋外)に位置
小児の場合, referenceとgroundは, 主に白質に位置する接点
頭皮上EEGの同時記録は, 必須ではない
サンプリング周波数は少なくとも256Hz, 理想的には512Hz
発作間欠期異常や発作の確率を高めるために, 過換気 (3-6分) を行う必要がある
電気刺激
発作再現, 機能マッピングが主な目的
電気刺激は, 自発的な発作後に行う
電気刺激は, 双極, 二相性電流を使用して, 電極の2つの連続した接点間で実行
shock stimulation (低周波) の通常パラメータ
(1)1Hzの周波数
(2)shock持続時間0.5-3 ms
(3)0.5-4 mA
(4)stimulation持続時間20-60 s
train stimulation (高周波) の通常のパラメータ
(1)50Hzの周波数
(2)shock持続時間0.5-1 ms
(3)0.5-5 mA
(4)stimulation持続時間3-8 s
特に海馬やFCDにおける発作の誘発, 機能マッピングに役立つ
全般性強直間代発作を誘発するリスクがあるため, 中枢領域ではトレイン刺激を慎重に使用する
短くて低強度のトレインのみを使用
ベースラインに戻るまで, 刺激を待つことが重要
機能マッピングは, 特定の刺激に対する誘発活動 (誘発電位, 振動活動) を記録することで補完できる
非協力的な子供の場合, 睡眠中にトレイン刺激を使用して, 運動野の位置特定を行うことができる
SEEGの解釈
referential montage, bipolar montageなどを使用
IEDsの鋭さ, 持続時間, 振幅, fast activitiyとの関連性などを分析する
解剖学的分布と各領域での頻度を調べる
各脳領域で背景活動を分析し, 遅延や変化を調べる
発作時脳波は, low voltage fast activityが多い.
発作後期の局所的な電気的抑制や遅延は, 局所化の価値が高い可能性がある
最初の電気的変化は, 臨床症状に先行して起こらなければならない
無症候の発作時脳波は, epileptic zoneを定義するのに役立つ可能性がある
電気刺激は, epileptic zoneから離れた領域を刺激しても, 発作が誘発される可能性がある
刺激によって発作がないことは, epileptic zoneを定義するための予後価値はないが, てんかんの病因に依存する可能性もある
発作開始の分析は, epileptogenicity index (EI) やgamma activity mapを利用することもできる
[Isnard J, Taussig D, Bartolomei F, et al. French guidelines on stereoelectroencephalography (SEEG). Neurophysiol Clin. 2018 Feb;48(1):5-13. doi: 10.1016/j.neucli.2017.11.005. Epub 2017 Dec 23. PMID: 29277357.]
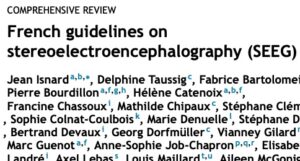
コメント